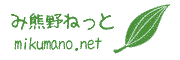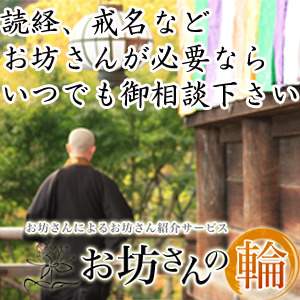女人高野、那智妙法山

那智山スカイライン(有料道路でしたが、2007年4月1日より無料化)の終点の駐車場に車を止め、杉木立に囲まれた参道を登っていきます。じきに山門が見え、本堂が見えてきます。熊野那智大社や青岸渡寺が観光客で賑わっているときも、ここは訪れる人も少なく、静けさを保っています。
那智三峯のひとつ、標高749mの妙法山。その山頂近くに建つ妙法山 阿弥陀寺。弘法大師空海が創建したと伝えられる真言宗の古刹です。
弘法大師は高野山開創の前年(815年)、那智を訪れ、那智の山中や滝で修行し、妙法山の山頂に卒塔婆を立てたと伝えられ、また阿弥陀如来像を彫られたとも伝えられます。
阿弥陀寺の本尊である阿弥陀如来像は平安時代の作と伝えられていましたが、1980年代に火災で焼失してしまったそうです。
女人禁制の高野山の代わりに女性が多く参詣したので、女人高野と呼ばれました。熊野古道最大の難所、本宮へ向かう「大雲取越え・小雲取越え」の出発点でもあります。
亡者の熊野参り

ここはまた死者の霊魂が詣でる寺でもありました。
「亡者の熊野参り」といい、人が死ぬと、その魂は、枕飯3合炊く間に、枕元に供えられたシキミを1本持って、この寺を詣で、釣鐘をひとつ、つき、そして、持ってきたシキミを妙法山山頂に建つ奥ノ院・浄土堂に供え、それから大雲取越えの山路を歩いていくといわれます。
阿弥陀寺の鐘は人陰もないのに、時折、かすかな音を立てるといわれ、また、死者が供えたシキミのために奥ノ院付近はシキミが生い茂るようになったと伝えられます。
奥ノ院・浄土堂へは、大師堂を経て、山道を20分ほど登ります。大師堂は室町時代、永正6年(1509年)の建立。
 大師堂
大師堂
 浄土堂
浄土堂
日本最初の焼身往生の場

本堂から数十m離れたところ、大師堂の近くには2m四方ほどの石の囲いがあります。唐から来朝した応照上人の火定(かじょう)跡です。
火定とは、生きながらに身を焼き、浄土へ往生することをい、応照上人の火定が、日本で行われた最初の焼身往生だといわれています。
応照上人の火定の有り様は『大日本国法華経験記』に以下のように記されています。
大日本国法華経験記 現代語訳
那智山の住僧、応照は、諸仏を供養しようとその身を焼いた。
体が灰になっても経を読誦する声はたえず、鳥が数百羽集まって来て声を合わせて鳴き飛ぶなどの不思議が起こった。
これが日本最初の焼身往生である。
この日本最初の焼身往生が行われたのがこの石囲いの場だということです。
死出の山路
阿弥陀寺から本宮へと続く「大雲取越え・小雲取越え」の道は、「死出の山路」と呼ばれ、その道中には「亡者の出会い」と名付けられた場所さえあり、道行く人はときに、亡くなった肉親や知人の霊に出会うことがあるといわれます。
阿弥陀寺御本尊阿弥陀如来の御詠歌は、
くまの路をもの憂き旅とおもふなよ 死出の山路でおもひ知らせん
熊野詣を気の進まない大変な旅だと思うなよ。熊野詣は旅そのものが大切なのだよ。死出の山路(「大雲取越え・小雲取越え」の道)で、私(阿弥陀如来)があなたに熊野詣の旅のありがたさを教えてあげよう。
中世、熊野は浄土の地であると見なされ、熊野(=浄土)に入るには、儀礼的な意味で、いったん死ななければなりませんでした。
そのため、熊野詣は「葬送の作法」をもって行われました。熊野詣は死門への旅だったのです。
中世の熊野詣は、生きながらに、死んで浄土に生まれ変わって成仏し、そして、再び現世に帰っていくという構造を持っていました(詳しくは、熊野入門の「熊野詣とは何?」をご覧ください)。
ですから、熊野三山の社殿に参詣することはもちろん大切なことだと思いますが、それ以上に、熊野に到るまでの精進潔斎して歩く道中の日々こそが、大切なのだという気がします。
熊野詣とは、生きながらに、死んで浄土に生まれ変わって成仏し、そして、再び現世に帰っていくという道程そのものであり、目的地にではなく、旅そのものにこそ熊野詣のほんとうのありがたさがあったのだと思います。
ある目的を求めて行動し、その目的を達成できなかったとしたら、その行動は無駄であったのか。虚しい時間を費やしたことになるのか。結果がすべてと考えるのなら、それはたしかにその通りでしょう。
しかし、目的はその人に進むべき方向を与えるだけだと考えれば、たとえ目的を達成することができなかったとしても、行動そのものが充実していれば、その行動を無駄なものであったと考えることはないのではないでしょうか。
そのようなことも阿弥陀寺の御詠歌は考えさせてくれます。
(てつ)
2002.10.30 UP
2003.11.26 更新
2003.11.29 更新
2004.2.2 更新
2013.7.22 更新
2019.11.5 更新
参考文献
- 神坂次郎『熊野まんだら街道』新潮文庫
- 妙法山阿弥陀寺HP
妙法山阿弥陀寺へ
アクセス:JR紀伊勝浦駅から車で約30分(那智山スカイライン有料無料)
徒歩で行きたい方は、那智山青岸渡寺の裏手の熊野古道「大雲取越」を徒歩10分ほど行くと「左、妙法山 大雲かけぬけ道」の標石があり、そこから左の脇道を徒歩20分くらいでたどり着いたと思います。
駐車場:無料駐車場あり