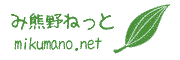かつては十二所権現と呼ばれた村の鎮守

JR武蔵野線東川口駅より北へ徒歩20分ほど。
大門神社は旧大門村、下野田村の鎮守で、大門宿に鎮座します。
江戸時代は日光御成街道の宿場町として栄えました。
神社へは倉庫の間を入ります。赤い鳥居と長い参道が境内まで延びています。



大門神社の拝殿には、左甚五郎作と伝えられる龍の彫刻があります。

境内には愛宕神社、御嶽社、浅間社、天神社、稲荷社などの境内が点在しています。
御祭神
不詳
往時の社名は熊野十二所権現に由来するものとおもわれ、本山派修験として勢力のあった中尾村の玉林院の活動が創立の背景にあったと考えられる。「明細帳」では祭神を、天神七代、地神五代の合わせて十二柱としているため、明治初年の神仏分離を機に改めたことが推測される。
(「埼玉の神社」による)
御由緒
不詳
「新編武蔵風土記稿」大門宿の項には
十二所権現 村の鎮守なり。
別当 華蔵寺 熊野山 宝光院と号す。
と記述されています。
明治40年6月14日 地内の10社を合祀したことにより改称しました。
(TATSUさん)
No.1142
2009.11.28 UP
2025.3.20 更新
参考文献
- 『埼玉の神社』
- 『新編武蔵風土記稿』