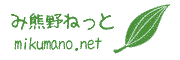奇絶峡は植物活状学にもっとも有用の所に候

奇絶峡
奇絶峡(きぜつきょう)は植物活状学にもっとも有用の所に候。これはエコロギーと申し、近来発達の学問にこれあり。小生が一昨々年ロンドンで一寸発端を出し置き候如く植物と植物と相互の関係を知る事もっとも必要、また植物と動物、植物と無機物との関係を見るにももっとも必要なり。
ー 「奇絶峡保勝に関し南方先生より本社毛利に寄せられたる書」『牟婁新報』大正5年(1916年)9月23日付
田辺湾に注ぐ会津川の支流・右会津川の上流にある峡谷の、約2kmにわたって奇岩・巨岩が見られる区間を奇絶峡と呼びます。奇絶峡は南方熊楠が将来に残すべきだとした景勝地で、現在、「南方曼陀羅の風景地」を構成する風景地のひとつとして国の名勝に指定されています。
熊楠が神社合祀反対運動に奔走していた頃、奇絶峡に水力発電所の建設計画が立てられました。熊楠は、奇絶峡はいずれ多くの観光客が訪れる景勝地となるはずだからと、建設に当たっては景観に配慮することを求めました。さらには奇絶峡はエコロギー(エコロジー、生態学)の研究に役立つ場所だから保全しなければならいのだとも主張しました。
「近来発達の学問」である、と熊楠が説明しているように、エコロジーという学問はこの頃まだ黎明期にありました。エコロジー(生態学)にとって基本的な概念であるエコシステム(生態系)という言葉すらまだない時代でした。熊楠はエコロジーを「植物と植物と相互の関係」を知り、「植物と動物、植物と無機物との関係」を見る学問であると説明し、その研究のために奇絶峡は本当に役に立つ場所だと熊楠は主張しました。
日本で最初にエコロジーを紹介したのは、東京帝国大学教授の三好学だといわれます。三好学は明治41年(1908年)に出版された『植物生態学』のなかで Ecologyを「生態学」と訳して紹介しています。
エコロジーという言葉を造ったのはドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルです。熊楠は三好学の著作からエコロジーを知ったわけではなく、在米・在英時代にヘッケルの著作からエコロジーという学問を学んでいました。
ここでは熊楠はエコロジーを「植物活状学」と訳してますが、以前には「植物棲態学」と訳していました。
実に世界に珍奇希有のもの多く、昨今各国競うて研究発表する植物棲態学 ecology を、熊野で見るべき非常の好模範島なるに、……終にこの千古斧を入れざりし樹林が絶滅して、十年、二十年後に全く禿山とならんこと、かなしむにあまりあり。
ー 柳田國男宛書簡、明治44年(1911年)8月7日付『南方熊楠全集』8巻
エコロジーを三好学は「生態学」と訳し、熊楠は「植物棲態学」と訳し、その後、「植物活状学」と訳しました。これにどのような意味があるのか、私にはわかりません。しかしながら、エコロジーという学問の捉え方が2人の間で微妙に異なる部分があったのかしれません。
三好学も南方熊楠も日本における自然保護運動の先駆者ですが、三好学が行った自然保護運動・天然紀念物保存運動は1本の大樹や珍しい動植物、特定の個体や特定の生物種の保護であり、熊楠の行った自然保護運動・神社合祀反対運動は森全体の保護を目指したものでした。
(てつ)
2024.5.14 UP
参考文献
- 『牟婁新報』
- 紀南文化財研究会『熊野』第151号
「奇絶峡保勝に関し南方先生より本社毛利に寄せられたる書」を所収 - 『南方熊楠全集』8巻、平凡社