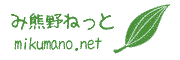死者の霊魂が詣でる寺
鎌倉時代の説話集『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』にはこんな話があります(巻第一 神祇・二七)。
盲人熊野社に祈請、夢に先世の報を知らされ、懺悔して明眼を得る事
熊野(おそらくは本宮か)に、盲目の者で、斎燈(さいとう:神前のかがり火)を焚いて眼が見えるようになることを祈る者がいた。この勤めが三年になるけれども、効果がないので、権現を恨み申して、ふと眠って見た夢に、
「汝が恨むのはもっともではあるけれども、前世の報いを知るべきである。汝は日高川(和歌山県日高郡を流れる川)の魚であったのである。かの川の橋を熊野詣の道者が渡るので、『南無大悲三所権現(三所権現は本宮・新宮・那智の総称)』と上下貴賤の諸々の人々がお唱えになる声を聞いて、その縁によって魚であった身がたまたま受け難い人間の身に得た。この柴燈の光に当たる縁をもって、また来世に明眼を得て、次第に昇進するはずである。このことをわきまえないで、みだりに我を恨むのは、おろかである」
と、戒めなさると見て夢から覚めた。その後、懺悔して死ぬまでもと決心してこの斎燈を焚く役を勤めたところ、眼も見えるようになった。
熊野は盲人や癩者をも回復させることができる強力な浄化力をもつ場所だと考えられ、多くの盲人や癩者たちが治癒の奇跡を求めて熊野を詣でました。
平安時代末の貴族、藤原宗忠(むねただ)の日記『中右記(ちゅうゆうき)』には、天仁二年(1109)条に熊野参詣の様子が記されていて、それには、道中、岩神王子(熊野古道・中辺路にある王子。本宮まであと約5時間)で盲人に出会い、その盲人が熊野詣の途中で食料が尽きてしまったというので、食料を与えたということが記されています。
また、熊野本宮大社の近くには、盲目僧形の芸人、琵琶法師が祖神とした天夜尊(あまよのみこと)の旧跡と伝えられる場所がありました。大智庵という寺がそれで、琵琶法師の総本山とされていたと伝えられています(中世以後、幕府公認で、盲人により組織された団体「当道(とうどう)」の根本史料『当道要集』を後に考証した『当道秘訣』巻下に記載された「熊野本宮光神山天夜尊御旧跡縁起」による)。大智庵は今は無住。
天夜尊は、仁明天皇の第四皇子の人康親王(さねやすしんのう)のことだそうです。詩歌管絃にすぐれた人康親王は、失明後、盲人たちに琵琶や朗詠を教えて、彼らに生活の道を与えたといわれています。そのため、人康親王は、盲人たちに崇められ、彼らの祖神として祀られるようになったそうです。
琵琶法師の総本山が熊野本宮にあったと伝えられているということ。
実際、琵琶法師が語る『平家物語』には熊野信仰の影が色濃く落とされています。琵琶法師にとって熊野信仰が心の支えになっていたように思えます。
熊野を詣で、開眼した人もいれば、開眼しなかった人もいたことでしょう。目が見えるようになった人というのはほんとうにわずかな人数しかいなかったように思います。しかし、実際に開眼することがなくとも、熊野信仰が目の見えない人に精神的な癒しを施していたということはあったと思います。
(てつ)
2002.8.29 UP
2002.12.9 更新
2003.6.20 更新
2023.1.26 更新
参考文献
- 西尾光一・小林保治 校注『古今著聞集 (上)』新潮日本古典集成
- 小山靖憲『熊野古道』岩波新書
- くまの文庫2『熊野中辺路 伝説(上)』熊野中辺路刊行会