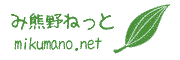地域の住民たちが守った田の中の神の森

田中神社。その名の通り、水田の少ない熊野では珍しい、田の中にある神社。
熊野参詣道(熊野古道)中辺路(なかへち)の三栖王子(みすおうじ)から岩田川に抜ける岡道(おかみち)沿い、八上王子(現八上神社)と稲葉根王子(いなばねおうじ)の中程辺りに、田中神社はあります。
和歌山県上富田町岡、国道311号線から岡川(おかがわ)に沿って遡る県道沿いに、周囲を田に囲まれてぽつんとある8アールほどの小さな森。それが田中神社です。
江戸時代の紀伊国の地誌『紀伊続風土記』に田中神社は次のように記されています(現代語訳てつ)。
田中明神社
境内森周二百五十間
宮代という所にある。祀神は弁財天という。一村の産土神とする。拝殿がある。
田中神社は江戸時代には田中明神社といいました。明神とは仏が神として明らかな姿で現れたものという意味です。本体は仏であり、明治初期の神仏分離政策により明神という言葉が使えなくなって、田中神社と社名を改めました。
田中神社の森の中に入ると、神社というのは建物ではないのだということがわかります。田中神社にも小さな社殿はあるのですが、それよりもこの周囲の木々が聖なる空間を形作っているのだということが実感できます。
田中神社は昔、田中神社から六キロメートルほど上流にある岡川八幡神社の上手の倉山という山から、大水のときに森全体が流れ着いたのだと伝えられます。 流れ着いた森を神社として祭ったのが田中神社の始まり。まさに神社というものは森あってのものなのだということを田中神社の小さな森は教えてくれます。
古代の日本人が神様と出会う場所というのは建物の前や内部ではなく、森のなかにぽっかりと空いた、木々に囲まれた空間であったのだと想像されます。おそらくは森のなかにぽっかりと空いた空間が神社の始まりでした。
田中神社には小さな社殿がありますが、本来神社というのは森だったのだということを田中神社の小さな森は気づかせてくれます。
神社合祀に抵抗

南方熊楠は田中神社について次のように述べています。
この辺に柳田国男氏が本邦風景の特風といえる田中神社あり、勝景絶佳なり。
(松村任三宛南方熊楠書簡、明治44年8月29日付『南方熊楠全集』第7巻、口語訳はこちら)
田の中にこんもりとした神社の森があるという日本に特有の風景を、熊楠は「勝景絶佳」と称賛しました。
しかしながら、この田中神社の森にも、やはり明治末期には伐採の危機が訪れました。何者かが県に合祀の申請を行い、明治41年(1908年)11月26日に田中神社の八上神社への合祀が県から許可されました。この合祀許可が滅茶苦茶で、合祀先の八上神社も同日に松本神社という他の神社への合祀が許可されているというデタラメさでした。合祀先の八上神社自体がもうすでに廃社となることが予定されているのです。
田中神社の氏子たちの大部分は合祀に反対で、合祀許可がなされた後も合祀を決行せず、森も社殿も残し祭祀も行って、合祀に抵抗しましたが、結局合祀され、大正4年(1915年)12月25日に合祀済届出がなされました。それでも氏子たちは森も社殿も残し、祭祀を続けました。
岡往来は熊野古道であって、古え帝皇の車駕を迎うること幾百回なるを知らず。今に御車坂のあるを見ても盛んな古えの熊野がしのばるるでないか。ことに同村岡川の八幡神林のごときは本邦希有の天然林である。同村岡の田中神社のごときも、古代暦学上の記念物かとも思わるるほどのもので、コンナことは素人に話しても分らぬが、大切に保存せねばならぬ地区である。
(「岡の田中神社をツブしちゃ困る……南方先生の談話……」 『牟婁新報』大正5年1月13日付)
熊楠も合祀後も田中神社の合祀に反対し、森の保護を訴えました。
今回田中神社を八上神社に合祀したについて、その跡森を伐採して八上の神田とすると聞き及ぶ。この田中神社と八上神社と岡川八幡神社の写真は、かつて『日本及日本人』にも載せ、また前代議士中村啓次郎君より時の内務大臣平田男に示して讃称を得たこともあり、かかる古社はなるべく保留を望むとの言なりし。
かつ理学博士白井光太郎君が特にその写真を複製して、井上前神社局長や徳川頼倫侯に示され、今も史蹟名勝保存会に保存されおり。
田中神社の風景美観と紫藤の優雅なること、幷びに現時植物学上の大問題たる松葉蘭発生研究に最好の場所たること、……
(「岩田村大字岡の田中神社について」『南方熊楠全集』第6巻)
田中神社の森の美しさや植物学上の価値を熊楠は訴えました。マツバランは根もなく葉もなく茎だけの、はじめて陸に上がった植物がそのままの姿で生き続けてきた「生きた化石」といわれる最も原始的なシダ植物です。
岡の出身で「熊楠菌類四天王」のひとりである樫山嘉一に、熊楠は以下のような助言を与えています。
神社の一件は、岡川の方は大丈夫保存の筈なるも、田中の方は一寸分らず……この際貴下の名を少しでも出すはよろしからず、とにかく役人など申す者は、穴ほりさがして何でもなきことに人をにくみ、それがため、免職などになりし例も少なからず。故に後日のことは後日と致し、この際貴下の名を少しも出さぬよう致し居り候間、この事御承知置きくだされたく候。
(樫山嘉一宛南方熊楠書簡、大正5年1月15日付『改訂 南方熊楠書簡集』紀南文化財研究会)
前面に出て神社の森の保護を訴える熊楠がいたから、氏子たちも役人の命令に背いて抵抗することができたのでしょう。氏子たちにとって熊楠の存在はとても心強かったはずです。
熊楠や氏子たちの奮闘により伐採を免れた田中神社の森は戦後、その価値を認められ、昭和31年(1956年)に和歌山県の天然記念物に第1号として指定されました。
南方熊楠の命名のオカフジ
 2022年4月20日撮影
2022年4月20日撮影
田中神社の森は全体を藤で覆われており、この藤は「オカフジ」と呼ばれてます。オカフジは当地での呼び方で、標準和名は牧野富太郎によって命名されたヤマフジ。
過日御将来の紫藤は、小生自ら色々取調べたるところ、間違いもなくキフジ、オカフジと本草図譜巻二十九に出おるものに候。丁度大字岡に産する故オカフジという名が宜しき様に思うも、牧野博士はこれにヤマフジと名を付けあり、小生は既に古くよりキフジ、又オカフジなる名称があるに、昨今ヤマフジと命名するは、如何と存じ候。(こればかりがどこの山にも生ずるに非ず、他所は知らず、紀州には山に生ずるフジは多くは例の穂が長きものなればなり) この事一度牧野博士へ問い合わすべきも、とにかく小生はオカフジという古い名がよいと存じ候。
(樫山嘉一宛南方熊楠書簡、昭和6年10月18日付『改訂 南方熊楠書簡集』紀南文化財研究会)
牧野富太郎はヤマフジと命名したが、江戸時代後期に刊行された日本最初の植物図鑑である『本草図譜』にはオカフジとあり、自生地の地名も岡なのでオカフジがよかろう、と。そのような熊楠の言葉により当地ではこの藤をオカフジと呼んでいます。 田中神社のオカフジが花を咲かせるのは5月上旬ころ。
 2022年4月20日撮影
2022年4月20日撮影
オカフジの特徴は普通の藤よりも花序(枝についた花の集団)が短いこと。ひとつひとつの花について見ると花弁がやや大きく、色は淡く、翼弁の色は反対に濃いこと。
 2022年4月20日撮影
2022年4月20日撮影

2009年4月27日撮影
2000年前の古代ハス
6月下旬~8月上旬ころなら、神社の森の裏手にあるハス田で、大賀ハス(おおがはす)の花を見ることができます。
大賀ハスは、昭和26年に千葉市検見川の地下6mにあった2000年前の縄文遺跡から、東京大学農学部教授であった大賀一郎博士がハスの種を発見し、発芽生育開花に成功させたものです。

2003年7月10日撮影

2002年7月19日撮影

2013年7月29日撮影
(てつ)
2003.7.11 UP
2009.4.27 更新
2009.10.27 更新
2013.7.29 更新
2015.2.1 更新
2015.4.6 更新
2021.2.26 更新
2022.4.22 更新
2024.4.20 更新
参考文献
- くまの文庫2『熊野中辺路 伝説(下)』熊野中辺路刊行会
- 南方熊楠 著、中沢新一 編『南方熊楠コレクション 森の思想』河出文庫
- 紀州語り部の旅 上富田町
- 『南方熊楠全集』第6巻、第7巻、平凡社
- 『改訂 南方熊楠書 簡集』紀南文化財研究会
田中神社へ
アクセス:JR紀伊田辺駅からバス、紀伊岩田バス停下車、徒歩約10分
駐車場:無料駐車場あり