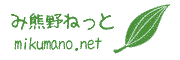熊野権現の御子神
王子とは、熊野権現の御子神だと考えられています。
熊野詣が一大ブームとなった院政期に、多数の王子が紀伊路・中辺路ルートに出現しました。
それらは総称して熊野九十九王子(くまのくじゅうくおうじ)と呼ばれました。九十九というのは実際の数ではなく、「数が多い」という意味ですが、実際、最盛期には99に近い数の王子がありました。
各王子では、奉幣(幣を奉る)と経供養(般若心経などを読む)などの儀式が行われ、里神楽や馴子舞、和歌会などの奉納が行なわれることもありました。
とくに格式が高い五体王子
九十九王子のほとんどの王子は、熊野十二所権現のうちの熊野五所王子(若一王子・禅師の宮・聖の宮・児(ちご)の宮・子守の宮)の1体を祀るものですが、5体すべてを祀るものもあり、それをとくに「五体王子」といいました。
「五体王子」は、とくに格式が高い王子だとして崇敬されましたが、どの王子が五体王子なのかは史料により異なります。「修明門院熊野御幸記」では籾井王子(樫井王子)・藤代王子・稲葉根王子が五体王子とされ、「後鳥羽院熊野御幸記」では藤代王子のみが五体王子で、稲葉根王子は五体王子に准じるとされます。
院政期の熊野ブームが生みだした王子ですので、王子の大半が院政の終焉とともに衰退していきました。
王子は法王子から
王子について南方熊楠は仏教の経典にある「法王子」に由来するのだとの説を唱えています。
熊野九十九王子など申す(この田辺付近だけにも出立王子、上野山王子、蟻通し王子、麻呂王子、三栖王子、八上王子、岩田王子など多くある)、この王子も、もと仏経より出でし語にて、神の子をまつりしとの義にあらず。菩薩はもと梵語ボジサットア(菩提薩多と音訳す)を約め音訳せるにて、旧くはこれを法王子と意訳せり。例せば、『大方等陀羅尼経』に、「南無釈迦牟尼仏、南無文殊師利法王子、虚空蔵法王子、観世音法王子、毘沙門法王子、云々、かくのごとき菩薩摩訶摩薩(まかさつ)は、まさにその名を念ずべし」。両部神道には諸王子をこの法王子すなわち菩薩の現身と見たるゆえ、法を省いて王子とせるなり。すなわち出立王子は観世音法王子の現身という風に見立てたるに候。
ー 岩田準一宛書簡『南方熊楠全集』9巻
(てつ)
2008.3.16 UP
2008.10.18 更新
2025.9.17 更新
参考文献
- 小山靖憲『熊野古道』岩波新書
- 『南方熊楠全集』9巻