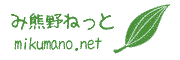藤原定家の後鳥羽院熊野御幸随行日記(現代語訳4)
後鳥羽院の建仁元年(1201年)の熊野御幸に随行した歌人、藤原定家(ふじわらのさだいえ、1162年~1241年)が書き残した日記『熊野道之間愚記(後鳥羽院熊野御幸記)』を現代語訳してご紹介します。5ページに分けて口語訳します。このページは10月17日か20日までの分。
- 藤原定家『後鳥羽院熊野御幸記』現代語訳1 京~藤白
- 藤原定家『後鳥羽院熊野御幸記』現代語訳2 藤白~田辺
- 藤原定家『後鳥羽院熊野御幸記』現代語訳3 田辺~本宮
- 藤原定家『後鳥羽院熊野御幸記』現代語訳4 本宮〜新宮〜那智〜本宮
- 藤原定家『後鳥羽院熊野御幸記』現代語訳5 本宮~京
熊野道之間愚記 略之 建仁元年十月
十七日 夜雨降り、今朝なお曇り、風がはなはだ寒い
明日、新宮へ下る。
船がまったくもってないとのこと。
御所のお召し以下みな人数を減らすとのこと。
(芝僧供の事)
病に倒れそうになるのをこらえて未の時(今の午後2時頃。また、午後1時から3時の間。一説に午後2時から4時の間)ばかりに御所に参る。
それよりも前に出御。芝僧供(※しそうぐ:「芝」は「目出たい」「尊い」の意。僧に供養すること。僧への供物)するとのこと。
御所〔西向礼殿である。殿上人は庭でお仕えする。公卿は左右にお仕えする〕の前庭〔両塔の前〕に東西に筵を敷いて行き、客僧の座とする。
山伏はおのおの自分の弟子を引率し、座を入れ替え、順番に引き出物を与えられる。すぐに立ってまた入れ替わる。
今日の人々はみな楚々とした(※清らかで美しい)装束を着(長袴、張下袴、供花(※くげ。仏前に花を供えること)の時のようだ)。
予はひとり知らず、日頃の御会の装束を着る。甚だ見苦しい。
この間に御前に参り、心閑かに礼して奉る。祈るところのものはただ生死を出離し、臨終の正念である。
(御前にお参りする事)
僧供が終わり、御前に参らせなさる。順番に御所作が終わる。
昨日のように還御。殿上人は前にいて、公卿はその後にいる。
次に山伏御覧。公卿・殿上人がまた御前の近辺にお仕えする。
山伏の(※入峰)作法は恒例とのこと。必要がないので詳しくは注せず。
〔渡御の前に乗船して山に向かって入る〕
寒風に術なし。
見終わってすぐに宿所に入る。
今夜は種々の御遊があるとのこと。
この先達が験競べを催すとのこと。
疲れているので宿所で臥す。
十八日 天気晴れ
(乗船の間の事)
明け方に宝前を拝む。川原に出て船に乗る。
〔宛てがいくださった船が1艘、予が個人的に雇った船が3艘、併せて4艘。供の下人らを多くとどめた。略定、侍3人、力者法師2人、舎人1人、雑人らである〕。
覚了房(阿闍梨)は老いに屈したと言っていまだ参らない。円勝房はともにしたがって行く〔精進屋よりともに来た先達である〕。
川の途中に種々の石などがある〔あるものは権現の御雑物と称する〕。
未の一点ころに新宮に着き奉拝。
(新宮に出御の事)
しばらくしていつもの通り御幸。前行して先ず宝前にお参りになる。
次に御所に入御。次いで立烏帽子。帰参してだいぶ経ってから出御(御奉幣の事)。御奉幣は本宮のよう。
予は前のように祝師(※神職)の禄を取る。事が終わって御経供養所に入御する間、私的に奉幣する。
人が多いことは例の如し。
帰参して、御経供養の布施を取る。
次に例の如く乱舞、次に相撲があり、この間に宿所に退き下がる。
夜に入って加持のため宝前に参る。僧らが散らばっていて、会に来ない。よって事情を問う。
先達に示して御所に参る。例の和歌が終わり退き下がる。また序がある。
十九日 天気晴れ
明け方に宿所を出て、また道に赴く〔輿を持って来たのでやはりこれに乗る。伝馬などがわずかに参る。師を順番に送る。先達・侍らはこれに乗る〕。
山海の眺望は興がないことはない。この道はまた王子が数多くいらっしゃる。
未の時(午後2時頃)、那智に参着する。
(那智に御参りの事)
先ず滝殿に拝す。
険しく遠い路で、明け方から食べていないので力がない。極めて術なし。次に御前を拝して宿所に入る。
しばらくして御幸とのこと。
日が入ったころ、宝前に参ると、御拝奉幣なさっている。
また祝師(※神職)の禄を取って、次に神供を供えさせる。
別当がこれを設けて取る。
(伝供の事)
公卿が順番に取り継ぐ。一万十万等の御前。殿上人がやはり順番にこれを取り継ぐ。予も同じくこれを取る。
次に御経供養所に入御。例の布施を取り、次に験比べとのこと。
この間に私的に奉幣し、宿所に退き下がる。
夜中に御所に参り、例の和歌が終わって退き下がる〔二座である、一は明日香(※阿須賀神社)とのこと〕。疲労病気の間は、毎時夢のようだ。
二十日 明け方より雨が降る
松明がなく、夜明けを待つ間、雨が急に降る。
晴れるのを待ったが、ますます雨は強くなる。
よって営を出て(雨が強いので蓑笠で)1里ばかり行くと夜が明ける。
風雨の間、路が狭く、笠を取ることができない。蓑笠を着、輿の中は海のようで、林宗のようだ。
1日中かけて険しい道を越える。心中は夢のようだ。いまだこのような事に遇ったことはない。雲トリ紫金峯は手を立てたようだ。
(紫金を越える事)
山中にただ一宇の小さな家がある。右衛門督(※藤原隆清)がこれに宿していたのだ。予は入れ替わってそこに入り、形のような軽い食事をする。その後、また衣裳を出し着る。ただ水中に入るようだ。この辺りで、雨が止んだ。
前後不覚。
戌の時(今の午後8時頃。また、午後7時から9時まで、または午後8時から10時まで)ころに、本宮に着き、寝に付く。この路の険難さは「大行路」以上だ。
記すいとまがない。
(てつ)
2009.2.19 UP
2010.10.29 更新
2020.2.18 更新
参考文献
- 熊野御幸記(読み下し)- ゆーちゃん(歴史好きの百姓のペ-ジ)
- 『本宮町史 文化財篇・古代中世史料篇』